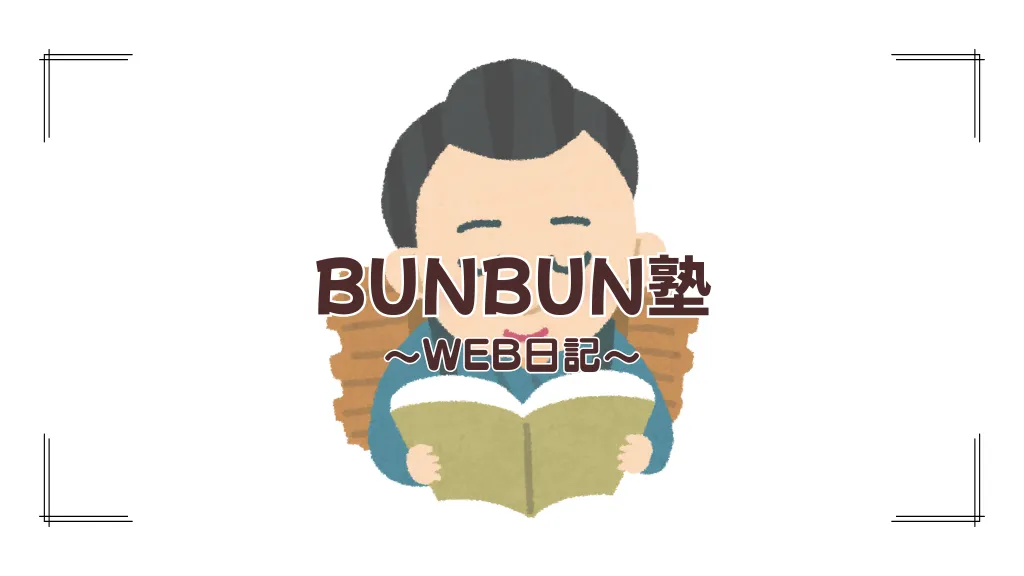塾名の由来
二宮金治郎(塾のアイコン)について

二宮金治郎は農民出身ですが、後に武士となり、600もの自治体の財政改革や農業改革を成し遂げました。
武士となった金治郎の剣の腕は分かりませんが、書を読み薪(まき)を運ぶ石像の姿は「勤労と学問」という意味において まさに文武二道の象徴です。
そんな金治郎は「実学」を尊び、「学問のための学問」を嫌ったと伝えられています。 子どもの実学といえば、まずは「家事」。
反対に、学問のための学問といえば、テストのためだけの勉強ということになるでしょうか。
当塾では、勉強はできても 家事を疎かにする子を高く評価しません。
(実際は、お手伝いをよくやる子は、お手伝いからの流れで、家庭学習に繋げられますから成績も上がります)まずは家のお手伝い。それから勉強ですね。
修身・斉家・治国・平天下

公教育の原点って何でしょう?
言うまでもなく、自分の幸せと公の幸せ その両方の追求ですね。
他に考えられるでしょうか。
「今の教育が、この子の幸せと社会の安定のために 本当に繋がっているのだろうか」という問いを私たち親や教師は止めてはいけません。
二宮金治郎が薪を背負いつつ読んでいる(といわれる)『大学』という中国の古典には、「修身・斉家・治国・平天下」という言葉があります。
良い家庭を作れるように自分を修め、国や社会が豊かになるような家庭を作り、世界が平和になるように国を作りなさい。。。という意味ですね。
まずは幸せな家庭作り。
これは、親と子供の共同作業です。
そして、親の気持ちが、適度に社会貢献に向いていること。
「自分の子どもさえ良ければ社会はどうでも良い」という親が増えれば、きっと子供の将来、住みにくい世の中になってしまいますから。
不易流行

当塾は基本的に 日本の伝統を重んじる方向性です。
ただ、単に古ければ良いという話でもありません。
最新科学の知見は大切です。
何百年も続いてきた伝統があるとすれば、そこには何か一定の価値があると考えますが、それでも、その伝統を鵜呑みにするなら、子供たちから「言ってることと やってることが違うじゃん」と言われそうです。
塾ではいつも「既成の価値感を疑え。自分の頭で考えろ」と言っているわけですから。
新しい科学の知見にも耳を傾けつつ、ただ、新しい知見はしょっちゅう上書きされますので、あまり惑わされずにやっています。
親孝行とお手伝い

子供がお手伝いをやってくれてもくれなくても、正直、親にとって どっちでも良かったりします。
洗い物などしてくれたひには、かえって二度手間になるだけ…だったりするわけです。
今の時代、そもそも親が「親孝行」なんて求めてないように思えます。
下手にお手伝いなんかされるよりも、いっぱい勉強して良い成績をとってくれた方が親としては嬉しいわけです。
こうして「褒められることはあっても、感謝される経験に乏しい子」
が育ちます。
でも、人から感謝されるって、自分には生きる価値があると実感できる、すごく確かな感覚です。
それを親から もらえないのは残念な気がします。
下の女の子の名前はメイちゃん(小6)。
塾生が里親になって、NPOを通じて小1の時から就学支援を続けているアジアの女の子です(塾生の頑張りがお金を生むシステムを作っています)。
メイちゃんは、学校から帰ると、帰りが遅い両親に代って洗濯・お掃除を済まし、お料理を作って両親の帰りを待つ毎日。
おまけに、成績も とっても良いんです。
「日本のお兄ちゃん・お姉ちゃんたちの恩に報いるために、勉強も頑張らなきゃ」って思って努力しているそうですし、これは、里親たる塾生たちの刺激にもなってくれていると思います。
塾生の保護者の皆様には、「二度手間になる」なんて言わず、子供に感謝したくなるぐらい、しっかり家事を教えて欲しいとお願いしています。
習慣こそ一生の財産

親が子供に贈ってあげられる最大のプレゼントは「良い生活習慣」だと思います。
子供は、その習慣をベースに その後の人生を生きていくわけですが、良い習慣はその子の人生を豊かなものへ導き、悪い習慣は その子の人生の足をひっぱり続けます。
しかしながら、それまでに身に着けてきた習慣を他の良い習慣に置き換えようと思っても そうそう簡単にはいきません。
ドアを開けっぱなしの癖、靴下やパンツを裏返しに脱いだまま洗濯物入れに放り込む癖、かばんの中にプリントをグチャッとつっこむ癖…
なんとなく、子供の将来の足をひっぱりそうではありませんか?
これらの悪癖を、塾オリジナルの「ルーティン表」というツールを使って、1つずつ狙いを定めて スモールステップで良い習慣に置き換えていきます。
恐さについて

パワハラという言葉に敏感な今の時代、子供の叱り方も 難しくなりました。
でも、子供を怖がらせるような叱り方は、本当に良くないのでしょうか。
改めて考えてみたいと思います。
なぜ改めて考えたいのか、、、理由は2つ。
1つめは、
怒鳴ったりは しないかわりに、不満げな声で小言を言い続け、親子ともにストレスが溜まっている家庭が多いように見えること。
「何度言ったら分かるんだろうねぇ」
「いい加減、注意するのにも疲れたわ」
パワハラではないけど、モラハラかもって思えますね。
身に覚えのある親、世の中には決して少なくないと思います。
もう1つの理由。それは「相手が居るときはどうか」か という話が曖昧だからです。
自分の子供が、クラスメイトに対して ずっと嫌がらせをしていたとして、そんな時、相手の親子に対して、
「うちの子には 粘り強く言って聞かせますので、それまで 待ってください」と言うのか、という話です。
逆の立場ならどうでしょうか。
自分の子供がイジメをされているとして、もし相手の親が、「ねばり強く うちの子に言い聞かせるので、直るまで 温かい目で見守って下さい」
と言われたらどうでしょう。
「ふざけるな!」って、なりませんかね。
そんな風に考えると、やっぱり 怒鳴ったり叩いたりの叱責も必要でしょうか。
すると、こんな意見が出てきます。
「子供を怖がらせるような叱り方をして、もし その子がPTSD(心的外傷後ストレス障害)になったら どうするんですか?」確かに、そうなったら いけませんよねぇ。
・・・ということは、以下のことだけは言えないでしょうか。
(話をしても分からない子に対して)ただ話を続けるだけでもダメ、怖がらせすぎてもダメ、つまり両極端はダメという話しです。
適切な言葉で、必要なら 適切な怖さも加える…その「適切さ」を模索するしかないように思います。
「道」という考え方

武道に限らず、華道・茶道など、日本の伝統には「道」という字が多く用いられます。
「道に終わりはない」とよく言います。
どういうことでしょうか?
ゴールはないので、死ぬまで修行だという意味もあるでしょう。
しかし、もう一つ。
「この道を歩いているなら それで良い」という意味もあるように思います。
目の前の子供たちを見ていて、いつも思うのですが、同じ努力をしても、うまくいく子と いかない子がいます。
そして、うまくいかない子は、すぐに自信をなくし、ひねくれて やめてしまいたくなります。
しかし、これでは、才能もなくて、努力もできなくて、しかも性格がひねくれた子が世に溢れることになってしまいます。
才能については、如何ともしがたいかもしれません。
しかし、あとの2つ(努力と性格)については、「ダメでもダメでも、諦めない自分はカッコいい」と思い込んでしまえば、なんとかなりそうです。
ダメでもダメでも諦めない生き方をしている時、それは「道」を歩いていることになります。
人生、なかなか うまくいきません。
「自分は『道』を歩いているか。歩いているなら それで良いではないか」
そんな風に思って、私たち大人も生きていきたいものです。
「継続は力なり」と言いますから、「ダメでもダメでも諦めない子供」…今風に言えば、レジリエンスが高い子供が増えてこれば、将来の日本、とても明るくなりそうです。